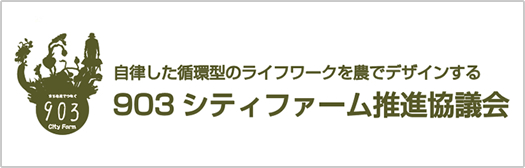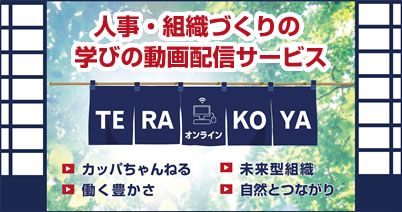2025年5月8日、労働安全衛生法の改正が衆議院で可決・成立し、従業員50人未満の小規模事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられることとなりました。これにより、これまで努力義務にとどまっていた小規模な職場でも、労働者のメンタルヘルスへの対応がより一層求められることになります。本稿では、この法改正の背景や意義、課題と対応策、そして「Community member Assistance Program(CAP)」の視点を交えて、その本質的な意義を探っていきます。
精神障害の労災認定の増加と小規模事業場の現状
2023年度、精神障害の労災決定件数は883件と過去最多となり、10年前の約2倍に達しました。特に小規模事業場では、メンタルヘルス対策の実施率が低く、10〜29人規模の職場ではわずか56.6%にとどまっています。全事業場の95.9%を占めるこれらの職場にこそ、包括的なメンタルヘルス支援が必要とされていたのです。
CAPの視点:支援から共創へ
ここで注目したいのが「CAP:Community member Assistance Program」の視点です。従来のように企業が一方的に「支援する/される」という構図ではなく、同じ地域や職場で働く仲間として互いに支え合う「共創的な関係性」をつくることが、今後のメンタルヘルス対策において重要になります。
CAPは、メンバー一人ひとりが「人生」と「キャリア」の交差点で安心して過ごせるよう、以下の3つの柱を提唱しています:
- 関係性(Community):共に語り合い、孤立しない関係性を育む
- 本物性(Authenticity):自分らしく居られる場を保障する
- 目的(Purpose):働く意味や人生の文脈に根ざした目的意識を支える
この視点は、単なるチェック項目の提出で終わるストレスチェックではなく、チェック結果をきっかけに「対話」が生まれ、「つながり直す」プロセスをどうデザインするかという問いを私たちに投げかけています。
義務化の概要とその意義
改正法では、ストレスチェックの対象が50人未満の事業場にも拡大され、2028年頃の施行が見込まれています。これにより、小規模事業場で働く多くの人々にも、セルフケアや早期対応の機会が広がります。
その狙いは、病気になる前に「気づきの場」を設けること。すなわち、心の不調を感じても「話せる」「頼れる」関係性をどう職場に根づかせていくかが鍵となります。
小規模事業場での実施に向けた課題と支援策
- プライバシー保護の難しさ:少人数ゆえに、誰が高ストレスと判定されたかが周囲に察知されやすい懸念があります。そのため、外部委託が原則推奨されます。
- コスト負担:ストレスチェックや面接指導の費用は一定の負担となりますが、地域産業保健センターの無料面接サービスなどの支援が拡充される予定です。
- 組織的対応の難しさ:配置転換などが難しい小規模事業場では、柔軟な働き方や休養の取り方など、現実的な対応をどう設計するかが問われます。
CAP的アプローチ:ストレスチェックを“関係性のメンテナンス”へ
ストレスチェックを単なる義務ではなく、「関係性の点検」と捉えることができれば、それは職場の空気を耕す大きな機会になります。たとえば、
- 結果をもとに、対話の場を設ける(個人ではなくチームとして)
- 「語り合える小さな場」(1on1や雑談タイムなど)を日常に埋め込む
- チェック結果を契機に、組織の“いずさ”(東北弁で違和感)を言葉にしていく
こうしたCAPの視点に立つと、メンタルヘルス対策は「制度の運用」ではなく、「場づくり」「関係性の再構築」という、もっと人間味ある営みとして捉え直せるのです。
2028年を待たずに始められること
施行は3年後でも、できることは今すぐにあります。たとえば、地域の支援機関とのつながりを持つこと。ストレスチェックをやる・やらないに限らず、「あなたがここにいてくれて嬉しい」と言葉をかけ合う文化を育てること。
CAPは、制度の有無を問わず、日々の関係性の中で機能し得る視点です。小さな職場こそ、柔軟さと温もりを活かして、メンタルヘルス対策を“その人らしい働き方”の実現へと昇華させていけるはずです。
これからの3年間は、チェック体制を整える時間であると同時に、“つながり”という土壌を耕す時間でもあります。CAPの視点を生かし、単なる義務を超えた、本質的なケアの文化を、私たち一人ひとりの職場から育んでいきましょう。