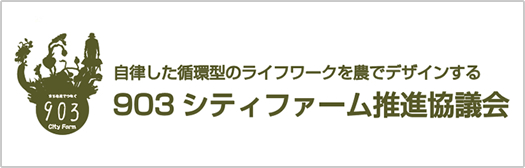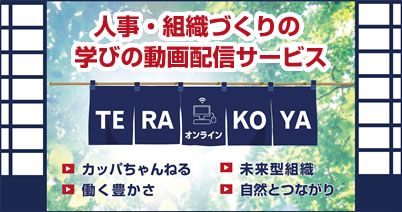近年、セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントに関する対策の義務が法改正で明文化されました。また、今年6月の法改正では、全ての企業にカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化され、1年6カ月以内に施行される予定です。
ハラスメントに対する事業主の対応が義務付けられたことにより、違反すると法律違反となり違反した事業主に対し厚生労働大臣からの勧告に従わない場合は会社名を公表できるという規定も設けられています。
マネジメントする立場としては「いかに対応していけば良いのか」と頭を悩ませるテーマだと思いますが、自社の事業構造や組織体制・風土・文化を踏まえ、制度・ルール面を見直してしくみ・環境の面から”ハラスメント問題を防ぐ“対応を考えていく必要があります。
ハラスメント対策はなぜ必要か
実際に会社でハラスメントが発生(セクハラされたと窓口に相談があったり、パワハラだという訴えがあったり)すると、加害者は、個人への名誉棄損として民法上の不法行為責任が問われたり、暴力や脅迫などで刑法上の責任が問われることがあります。被害者は、心や体に傷を負うだけでなく、退職に追い込まれたり社会復帰が困難になったりするケースもあります。
「事業主には、労働契約法という法律のもと職場で働く労働者に対する安全に働いてもらう環境を提供する安全配慮義務がある」という点を踏まえ、ハラスメント対策を考える必要があります。
<ハラスメント対策の一例>
(厚生労働省が推進している予防策を踏まえ弊社が編集)
(1)トップのメッセージ
企業(職場)のトップがハラスメント防止の重要性を発信して、方針を全従業員に伝え広めていく。書面・広報誌・社内メールなど、どのような形であっても全社員に伝わる手段であれば抑止力がある。
(2)制度・ルールの決定
企業と社員の双方で取り組みを進めるために、労使協定や就業規則などで明確にわかりやすく具体的に内容をまとめる。就業規則見直しに際しては、社員代表の意見を聴くことが必要だが、研修等の場を設け、社員全体にその内容を周知し、ハラスメントに該当する行為の定義、相談及び苦情の相談窓口を設けること、該当した場合の懲罰内容を理解してもらうことも重要
(3)実態把握
社員アンケートなどを実施して実態を把握する(全社員対象でも対象者を絞っても可)。アンケートは、実態把握のため匿名での提出が効果的。例えばGoogle フォームなどのツールを利用すれば、匿名のアンケートを手軽に実施できる。あるいは、産業医や安全管理者とのヒアリングや評価面接の際に、自己申告項目として設けることも有効。アンケート実施後は、結果を踏まえて研修の実施や相談窓口を周知するなど、必要な対策に活かす。
もしも問題が発生してしまった際の解決策
◇ 相談・解決の場の設置
社員が相談できるように窓口を設置(相談したことで不利益な取り扱いをすることは法律で禁止)。
窓口を内部に設置する場合は、人事労務部門・産業医・カウンセラーなどを対応のために設置。窓口を外部におく場合は、社会保険労務士事務所やEAPなどの専門相談窓口として代行しているものを利用。
| ハラスメント問題が生じた時の解決の段取り | |
| 1.相談 | 相談したことで不利益な取り扱いを受けることがないことを伝え、どのような対応をするか明確にしておきましょう。 |
| 2.事実関係の確認 | 相談者の了解を得た上で、行為者や第三者に事実確認し、それぞれの主張を合理的に判断する情報と考えます。 |
| 3.行為者・相談者へのとるべき措置 | 行為者又は相談者への注意・指導、行為者から相談者への謝罪、人事異動、懲戒処分など。懲戒委員会などを設け、状況を踏まえて総合的に判断しましょう。 |
| 4.行為者・相談者へのフォロー | 行為者・相談者の双方に対し会社の取組内容を説明し、理解を得て、繰り返し同様の行為が起こらないように、定期的な面談などのフォローが必要です。 |
| 5.再発防止の検討 | 本人の立場を配慮しながら行為者への再発防止研修を行い、可能であれば情報の発信をしましょう(→抑止)。 |
再び起こらないようにするために、行為者が同じような行動をする可能性が無いか、被害を受けた社員にとって安心・安全な環境になっているかどうか、などを注視し、対応を検討していきます。
今年から、厚生労働省はパワハラ指針を改正し、カスタマーハラスメントへの対応を企業に義務付けました(1年6か月内に施行予定)。悪質クレームや暴言などによって社員が精神的苦痛を受ける事例が増える中、企業には「相談窓口の設置」「被害者へのケア」「事前の研修やマニュアル整備」などの対応体制を整えることが求められます。“お客様だから”を理由に対応を放置・保留するのではなく、他のハラスメント対策同様、毅然とした姿勢を企業として示す必要があります。