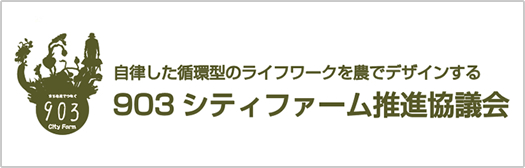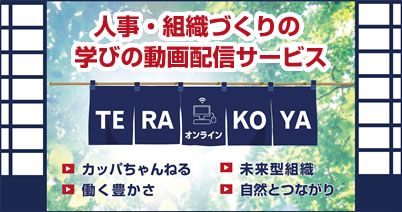高齢化が進む現代社会では、働き盛り世代が介護・看護の事情に直面する場面はますます増えています。そのような事情に対処しきれず社員が退職してしまうことは、職場にとって大きな損失であると共に、本人のキャリアが断絶し、生活基盤を脅かすなど、さまざまな課題を生み出します。
国は育児・介護休業法や介護保険制度を整備し、企業に“就労との両立支援”への対応を求めていますが、「身内のことだから人事や上司に相談しにくい」という心理的な壁や、「制度やサービスの情報が複雑で理解しづらい」「個々の状況に応じた介護・福祉の専門的アドバイスを受けるには時間も労力も足りない」など、課題は山積みです。
「会社が社員の家族のことまで考えないといけないのか!」と捉えるのではなく、「社員が自社で持続的なキャリアを歩んでいくために、社員と繋がりある家族や暮らし全般を捉えて対処を考えて行こう」と思考を転換して、これからの人事施策を考えてみましょう。
育児・介護休業法 ー 介護にまつわる制度の枠組み
育児・介護休業法(2025年4月改正)における介護にまつわる制度の枠組みとしては以下の通りです。
<介護休業制度>
・期間:要介護状態の家族1人につき通算93日まで(3回まで分割取得可能)
・対象家族:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
・介護休業中の経済的支援として、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
*支給額:休業開始時賃金月額の67% *支給期間:介護休業期間中(最大93日)
*申請先はハローワーク *介護休業終了日の翌日から2か月後の月末までに申請
<介護休暇制度(短期的な介護への対応)>
・取得日数:年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)
・取得単位:1日単位または時間単位
※法律上は無給だが、企業によっては有給の場合もある
<その他>
・所定外労働の制限
・時間外労働の制限(月24時間、年150時間以内)
・深夜業の制限
・所定労働時間の短縮等の措置
<下記が義務として定められています>
・雇用環境の整備: 研修実施、相談窓口設置、制度周知など
・早期情報提供: 40歳到達時の制度情報提供
・個別周知・意向確認: 介護申出時の制度説明と意向確認
福祉の側面
下記のような支援・サービスがあります。
<介護保険制度>
主な在宅サービス:サービス費用の1〜3割(所得に応じて)を利用者が負担
・訪問介護: ホームヘルパーによる生活支援 ・デイサービス: 日中の通所介護
・ショートステイ: 短期入所による介護 ・小規模多機能型居宅介護
<地域包括支援センターが提供するサービス>
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援
・権利擁護業務
・包括的・継続的ケアマネジメント
・家族介護者支援: 介護教室、家族会、相談支援
もし介護の事情が生じたら‥
✔ステップ1: 情報収集と相談
-会社の制度確認: 人事部に介護休業制度等を確認
-地域包括支援センターへの相談: 介護サービスの情報収集
ケアマネジャーとの連携: 介護計画の策定
✔ステップ2: 対応する時間をつくる
-突発的な介護で短期対応で足りる場合
介護休暇(時間単位取得)、有給休暇の活用、テレワークの実施、
-継続的な介護が必要で中長期の対応を要する場合
介護休業の分割取得、時短勤務、デイサービス・ショートステイの活用
介護保険サービスの本格活用、家族間での役割分担
✔ステップ3: 経済的支援の検討
-介護休業給付金の申請
-介護保険サービスの利用
-自治体の助成制度の活用、医療費控除・介護費控除の活用
「介護と就労の両立」
「介護と就労の両立」は、制度を知っているだけでは実現しません。事情が生じそうなタイミングでの早めの相談と、多様な制度・専門家を組み合わせた横断的な実践が重要です。
社員の家族にまつわる複雑な事情の対処を、会社だけで抱え込むことなく、地域資源を活用していくことが重要です。
そこで、社員には「相談窓口」がある安心感を、会社としては「地域や業界で専門家など地域資源をシェア」できる安心感がある仕組みとして、CAPを提案したいと思います。
CAPは、社員にとっては「制度やサービスをどう使えばいいか」を整理・検討するための伴走者であり、会社にとっては「離職防止と人材確保」のパートナーです。
まずは「もし必要があればこういうサービスがありますよ」と制度周知の機会として社員に示してみると良いと思います。