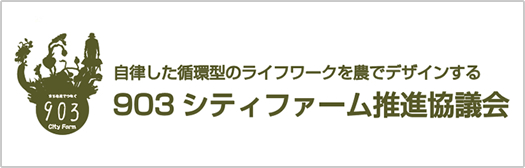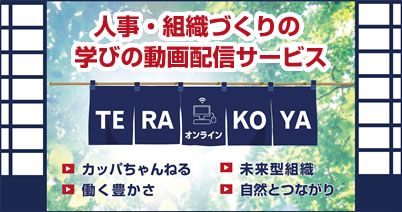人生100年時代と言われる今、その長い道筋においては、育児や介護といった家族の問題だけでなく、自身の病気など心身の健康とも向き合いながら、持続的なキャリアのあり方を考える必要があります。人事施策として「療養と就労との両立支援」という考え方が掲げられ、法制度も整備されたことで、さまざまな選択がしやすくなってきました。また、そのような方針を示すことで、“安心して働き続けられる会社”として採用においても好影響があると言えます。
========================================
2016年2月には、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省)」が発表され、“治療を必要とする従業員の就労継続による病状悪化を回避し、企業も適切な措置によって治療に対する配慮を行おう”という動きが促されました。
更に半年後には、働き方改革実現会議において、「病気の治療、子育てや介護と仕事の両立」の検討が表明され、2017年3月「働き方改革実行計画」では「7. 病気の治療と仕事の両立」が掲げられました。具体的には、①会社の意識改革と受入れ態勢の整備 ②トライアングル型支援(主治医と企業・産業医、両立支援コーディネーターの三角形で、罹患しながら働く人のサポートをしていくしくみ)などの推進 ③産業医・産業保健機能の強化 です。
<企業が両立支援を行なうために必要な“環境整備”>
- 会社としての基本方針等の表明と労働者への周知
- 研修等による両立支援に関する意識啓発
- 相談窓口の明確化等
- 休暇・勤務制度の整備
:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇などの休暇制度、短時間勤務制度、テレワーク、時差出勤制度、試し出勤制度などの勤務制度)
:社員から支援を求める相談・申し出があった場合の対応手順、関係者の役割の整理
:関係者間の円滑な情報共有のための仕組みづくり
まずは、自社の現状(実際に“両立支援”の検討が必要な社員がいるか、他社ではどのようなケースがあったか等)を把握し、方針を定めることが重要です。実際に事象が生じて初めて検討し、対応を決めていくケースが多いですが、その対応が前例として、その後の方針ともなり得ます。「あの社員だけは特別だった」などと対象者によって方針を変えていくことは、社員との信頼関係にも影響する可能性もありますので、予めある程度の事象を想定して、両立支援の方針を定めておくことは重要です。何か特別な制度を定めるのではなく、「有給休暇を既に使い切った社員が更に療養で休む場合に、特別な事情と認められれば、有給の特別休暇を与えるかどうか」「抗がん剤など頻度高く通院が必要な期間に、時差出勤や有休の時間取得を認めるか」など、労務上の観点からまずは検討しておくと良いでしょう。
<両立支援の進めかた>
自社の方針を定めた上で、社員の申し出を受け、両立支援の制度運用が始まります。
①「治療と仕事の両立支援」は、本人から支援を求める申出がなされたことから取り組みを始めることが基本です。そのため、まずは申し出がしやすい環境を整えることが重要です。
②対象者は、入院、通院、療養のための時間の確保が必要になるだけでなく、病気の症状や治療の副作用・障害等によって、自身の業務遂行能力が一時的に低下する場合もあります。そのため、時間的制約に対する配慮だけでなく、本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置の検討(働き方や業務内容の一時的な変更など)が必要です。また、それに伴って、収入面の懸念などさまざまな不安が広がることもあります。問題を整理しながら一つずつ対処すること、全てを会社が対応しようとせず、医療機関や家族、公共サービスなど複数の力でフォローしていくスタンスを大事にしましょう。
③社内ルールを設けるなど、両立支援の「対象者」と「対応方法」を明確にしておくことが必要です。同一労働同一賃金の観点から、ガイドラインは非正規労働者を除外するものではないことにも留意が必要で、自社においてはどのように対応するかあわせて検討します。
④両立支援を行なうためには、症状・治療の状況等の疾病に関する情報が必要です。これらは本人の同意なく取得できません(労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除く)。※2019年4月に施行された改正労働安全衛生法では「健康情報取扱規定」を定めることが義務付けられ、同意取得の手続きが明確に。
⑤さまざまな関係者が連携することで、症状や業務内容に応じた適切な両立支援が可能となります。企業における関係者(経営者、人事担当者、上司・同僚、社会保険労務士、産業保健スタッフ等)、医療関係者(主治医、看護師、医療ソーシャルワーカー等)、地域関係者(産業保健総合支援センター、治療就労両立支援センター、保健師、社会福祉士等)、さらには社員の家族など、関係者はさまざま存在します。そして、就労にまつわることだけでなく、医療、福祉など、扱う情報は多岐にわたります。経営者や人事担当者だけで対応しようとせず、また、上司に対応の負担が偏らないように配慮しながら、産業医や社会保険労務士、EAPコンサルタントなど専門家を活用し、連携体制に介在してもらうようにしましょう。
◆大切なのは、「いろいろと困難に直面しても、働きたいという意志があれば働き続ける職場である」というメッセージを示すことです。
経営者も社員も、家族や友人など周りで病気と向き合いながら前へ進んでいる人は必ずいるはずです。その時の本人の対応や周りの人たちのサポート、あるいは大変だったことなどを洗い出しながら、自社の社員が万が一の時は…というケースを想定していくと良いでしょう。
人材不足の時代、いま共に働くメンバーが持続的に自社で働き続けていくことを願って、両立支援の制度を考えてみましょう。